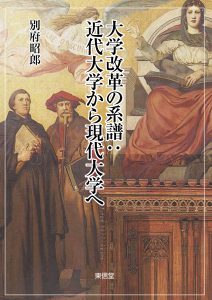別府昭郎著『大学改革の系譜:近代大学から現代大学へ』
教育学研究第85巻 第1号 p.83 書評より
本誌の書評執筆を引き受けた時、真っ先に評者の脳裏に浮かんだことがあった。それは20世紀アメリカの偉大な大学人であったカリフォルニア大学元総長クラーク・カーのドイツ大学への批判があまりに痛烈であったことである。
その批判は、エイブラハム・フレックスナー『大学論—アメリカ・イギリス・ドイツ』(玉川大学出版、2005年)の冒頭部「トランズアクション版への序文」においてであった。
この『大学論』は、坂本辰朗(創価大)、渡辺かよ子(愛知淑徳大)、犬塚典子(東北大)と評者の4人の分担訳になるものであった。その「序文」の訳出を担当したのは評者であって、その激しい論調が記憶に残っていたのである。しかもその批判は評者にも向けられていると自覚したものであった。
カーの批判は例えば、フレックスナーがドイツの大学をあまりにも崇拝しすぎ、見誤ったという。1930年代にはドイツの大学は、大学自身のふるまいによって崩壊し、国家における反動の中心としてファシズムへと向かっていったともいう。
評者は、こうした指摘を脳裏におきながら、カーの批判を合わせ鏡のようにして本書『大学改革の系譜:近代大学から現代大学へ』を読んだ。
本書の構成を各章のみ掲げ、節などは省略して示しておこう。
序章
第一部 ドイツにおける近代大学の成立
第一章 ドイツ大学史における18世紀の位置
第二章 19世紀に至るまでの私講師の系譜に関する考察
第三章 大学教師の精選とハビリタツィオンの導入
第四章 ドイツ大学史における公と私
第二部 古典的大学の創設と変容
第一章 ベルリン大学創設の理念
第二章 ベルリンにおける大学と学部概念
第三章 19世紀ベルリン大学における私講師
第四章 19世紀後半から1966年に至るドイツ大学史における学部構成
第五章 哲学部の歴史的変容—チュービンゲン大学の理学部の設置をめぐって
第三部 大学大綱法施行とボローニャ・プロセスの時代
第一章 大学大綱法下のドイツ大学教師の種類—歴史的パースペクトからの考察
第二章 大学大綱法下におけるドイツ大学の教育事情
第三章 大学の改革動向
第四章 現代ドイツにおける大学教師の養成・任命・任務・給与
終章
付論 歴史に学ぶ
本書はこのように3部構成となっているが、読者にとってありがたいのは、その3部構成と「付論 歴史に学ぶ」には、冒頭部に「解題」が付され、その各章には、章の要約や著者の問題意識などが記されていることである。章によっては、およそ30年も以前に執筆されたものがあり、各署の執筆された経緯も一様ではないが、著者が、本書を構成するのに際して読者に示したこの解題の利便性は、そのまま筆者の本書に込めた熱意とドイツ大学の歴史を伝えようとする情熱を感じさせるものである。
その想いは、序章においてドイツの大学が近代大学から現代大学へどのように変遷をしてきたかという問題意識のもとに本書を構成することであろう。
それでは著者にとって、近代大学とは何か。当然、そこには大学の歴史の時代区分の問題が先ず横たわっていよう。
著者は、ギーセン大学歴史学教授のP.モーラフの説を紹介している。そこでは、「古典期以前」の大学(プラハ大学から1810年のベルリン大学までの約460年間)、「古典期」の大学(ベルリン大学の創設から1970年前後までの約160年間)、「古典期以降」の大学(1970年以降の大学)という3段階の歴史歴憐買いが示されており、著者は、これに依存して上の目次のように再構成したのである。
つまり、1347年の神聖ローマ帝国最初の大学であるプラハ大学から、ボローニャ・プロセスの時代となった現在の大学までを詳細に分析しようとしているのである。その史的展開を3つの時代区分で解き明かそうとする試みが本書の挑戦である。モーラフ教授も、また著者も「古典期」の大学が中心に置かれているという。この時代がドイツの大学の黄金期であったからである。
序章では、ドイツの大学史を考える上で、第一には、「歴史主義と超歴史主義との関係」として捉えることを主張し、その歴史を史的変化の相として考える。これを歴史主義とすれば、また地方でフンボルトの大学理念に学びつつ、歴史を超越して現在大学の改革を推進できるという。これが超歴史主義である。
第二には、個別大学で言えることは、全ての大学でも言えるだろうかという問いである。例えば、19世紀中葉以降の哲学部の分裂については、個別的な問題として考えなければならないという。後にチュービンゲン大学における事例を詳細に検討するのは、その分裂に史的な意義があるからである。
第三に、大学の本質とは何か、という問題である。ドイツの大学は、中世史家ライナー・A・ミューラーによれば、教育機関であり学位授与機関であったという。しかも「教会の施設」であり、教授は教会の聖職禄から棒給を受けていた。大学は民主的な組織であり、かつ「自由な空間」であったという。これらがどのように「古典期」の大学、「古典期以降」の大学において変わっていくかが詳細に検討される。
中世からの大学がもっていたさまざまな特権は、例えば学位授与権などは、「大学の自由」に包括されるが、いま、その本質がわが国日本ではおおいに揺らいでいるとし、その現状に大きな危機感を隠さない。著者の大学への想いは、そのまま著者の立ち位置を示している。
第一部は、ドイツ大学の18世紀のもつ意味を問い、大学内部の変化、例えば学部の構成、講義の種類などについて、大学の内部から、ドイツ大学が歴史から逃れられないさまを、正確に描き出している。大学教授の養成と任命の方法、教授資格とドイツ大学に独特のハビタリツィオン(教授資格専門試験)、そして私講師制度の発生とその展開についてその系譜をたどっている。
第一部では、近代大学の揺籃期を描いているが、あらかじめ近代大学の特徴を14の指標で示している。近代大学についての定義と言い換えてもよいだろう。著者が示すのは、大学の国家の機関化、正教授支配の大学、法学部や哲学部の学内地位の向上、大学教師の世俗化と家族大学、新しい哲学や学問の勃興、大学の教育目標の変化、教授用語の変化、大学教授になる者の精選=競争原理の導入、研究の大規模経営などを挙げている。
さらに附属研究所の設置など5項目を加えて全14の指標を提示しているが、まさに著者の高い研究の到達である。
この到達点に立って、第二部においてはベルリン大学を中心にして、上の指標の変遷について分析を進めている。
仮にフレックスナーがドイツ大学について見誤ったとすれば、この時代であり、ベルリン大学についてであろう。フンボルト理念は、余りにも美しく、理想の高みにあり、ドイツ的といってもよいだろう。
「古典期」以前の大学とベルリン大学はどう違うのか。モーラフ教授のいうこの時代の大学は、聖職禄大学・家族大学であった。教授は聖職者と見做され、独身であり、教会から聖職禄つまり俸給を受けていた。家族大学であったともいうが、学問的業績より血縁が重視された大学を意味する。
新しい大学は、フンボルトの大学論などによって新たな精神が吹き込まれている。そしてベルリン大学は、伝統的古典的大学の原理と市場原理・国際化という新しい動向との戦いの場であるという。創設時代のベルリン大学は、中世大学の伝統的な4学部体制から成ったが、やがてドイツでは哲学部が分裂し、理学部のような新しい学部が誕生し、哲学部を欠く大学さえ誕生する。ベルリン大学には農獣医学部も加わる。社会や市場と向き合ったからである。
第三部では、現代の大学を検証するが、1970年代の大学大綱法施行による大学の変貌と事情を説き、ボローニャ・プロセスの受容によってEU圏内の大学としてドイツ大学を描いている。ここでも大学教師、学位などに言及している。この時代における大学の変革の背景には、アメリカの大学の影響もかすかに窺える。
カーが指摘したように、例えば1930年代におきた社会の変貌と大学内部の実態とについて十分に説いているか。あるいはドイツ近代大学の主たる機能のひとつとなった研究は、プロイセン官僚アルトホーフひとりによる奇跡なのか、学生の動向はどうであったのか。例えば、へ―スティング・ラシュドール『大学の起源』では、「中世における学生生活」と学生の人類に関する章が設けられていた。ドイツの学生は、平均して1年9ヵ月以上は在学しなかったと書かれている。学生の動向についてより詳細に書かれていればと思うのはないものねだりであろうか。学生間の決闘や学生牢などはドイツ大学を象徴しているようにも思えるからである。
フレックスナーは、『大学論』を閉じるに際して、自身のドイツ大学像が混乱しているからであると書いた。大学は歴史から逃れるわけにはいかず、ドイツの大学も逃れられなかった。アメリカの大学に研究をもたらした恩人でもあるフレックスナーでも誤ったのである。
フレックスナーが依拠したアメリカの大学は、研究を志向して大学院を創造したジョンズ・ホプキンズ大学であった。彼の母校であり、雨居r化のゲッチンゲン大学と呼ばれていたこともある。研究大学ロックフェラーを導いたのも彼である。
本書は、あたかも交響曲のように主題が繰り返され、時代に添って変奏されていく。大学教師、学部、学問分野、学位などの主題は一貫している。これら主題の変奏を重ねて、近代ドイツ大学から現代ドイツ大学へと改革をすすめる系譜を明らかに奏でてみせた。著者は、フレックスナーの轍を踏まなかったのである。
著者・別府昭郎の名は、1968年刊行の横尾荘英訳『大学の起源』(東洋館出版)の「訳者あとがき」に発見できる。世界中の学生が大学の変革を激しく求めていた時代である。
爾来、著者のドイツ大学への経緯とその実証的大学史研究は、わが国のこの分野の研究に大きく貢献している。本書は、著者の研究の集大成の一冊である。巻末に付された「付論 歴史に学ぶ」と「あとがき」は、著者の大学史への歩みを記しているが、読み落とすことができないものである。
(日本大学 羽田積男 評)
【東信堂 本体価格3,800円】